今日は遠藤周作の著書「海と毒薬」について感想を述べていきます。
この本、近代文学という大学講義で遠藤周作について取り上げられたときに購入したものです。
その時の講義では「沈黙」について取り上げられていました。
「沈黙」は近くの本屋に置いてなくて、代わりに「海と毒薬」を購入したんだったと思います。
実は読む前にネタバレをされました。
私は塾講師で、子どもに勉強を教えているのですが。
子どもの持っている国語のテキストに、ちょうど「海と毒薬」のラストシーンが。
問題を解説するには、当然読まなければならないので、ちょっと悔しかったです笑
遠藤周作
大学の講義や国語のテキストに載っているくらいですから、堅苦しい物語なのかも? と思われる方がいるかもしれません。
遠藤周作の描く物語は、良心や信仰・道徳のない世界の姿を以て読者を魅了していきます。
遠藤周作の生い立ち
幼少時代を満州で過ごした彼は、12歳の時、カトリック教会で洗礼を受けました。
評論家でありましたが、今回ご紹介する「海と毒薬」でキリスト教作家としての地位を確立すると、日本の精神風土とキリスト教の相克をテーマに、神の観念や罪の意識、人種問題を扱って高い評価を受けました。
代表作「海と毒薬」「沈黙」
先述いたしましたが、代表作に「沈黙」があります。
江戸時代、キリスト教を禁止していた時代に、外国からやってきた主人公が、日本のキリスト信仰―「神」信仰と自身の生まれ育った地の信仰の違いに葛藤し、苦しみ、悟りを経ていく物語です。
「海と毒薬」にも「沈黙」にも、精神的に苦しい言葉や残酷な場面、拷問の生々しさが含まれますから、苦手な方はどうぞ、ご注意ください。
海と毒薬
私が今回読みましたのは、講談社文庫出版の海と毒薬です。
あらすじ
生きたままの人間を解剖する―戦争末期、九州大学付属病院で実際に起こった米軍捕虜に対する残虐行為に参加したのは、医学部助手の小心な青年だった。彼に人間としての良心はなかったのか?
講談社文庫出版「新装版 海と毒薬」 遠藤周作著のあらすじ紹介より引用
私は医学を学んでいる人間ではありませんから、より一層手術の残虐なシーンなどが深く心を抉るように思われました。
残虐行為に及ぶまで、及んでからの人物の心情描写も詳細に描かれています。
グロシーンが苦手な方などは、読むことをお勧めしません。
倫理とは何か(ネタバレなしの感想)
倫理とは―日本における倫理とは「社会の総意」であるように感じました。
例えば何か悪いことが家庭内に起こった時、私たち日本人は
「世間体が悪い」「恥ずかしい」「世間を歩けない」「体裁が」
なんて言葉を使います。
幼い頃には「お天道様が見てるよ」なんて言葉もお聞きしたかもしれません。
日本における良心や倫理、道徳の柱は「誰かが見ている」という状況なのです。
その誰かは、隣人かもしれないし、学校の先生や友人、あるいは見知らぬ人かもしれない。
兎にも角にも「人からどう見られるのか」
それがキリスト信仰でいう「神」になり「良心」の礎になっています。
第二次世界大戦で、日本人は多くの他国の人々を殺し、戦争を不必要に長引かせた。
それでも現在、日本は「国」としての立場を保っています。
戦争期の日本人は「大衆が間違っていた」状況です。
そして先ほども記した通り、自身の良心が他人の価値観にゆだねられている日本人。
そんな人間たちが、正しき良心をもつことなどできるのでしょうか。
「海と毒薬」はマジョリティ―や全体主義の不安定を如実に物語っています。
印象的な言葉(ネタバレ有)
良心の呵責とは今まで書いた通り、子供の時からぼくにとっては、他人の眼、社会の罰に対する恐怖だけだったのである。
講談社文庫「新装版 海と毒薬」 遠藤周作著 142頁より引用
ぼくはあなた達にも聞きたい。あなた達もやはり、ぼくと同じように一皮むけば、他人の死、他人の苦しみに無感動なのだろうか。多少の悪ならば社会から罰せられない以上はそれほどの後ろめたさ、恥ずかしさもなく今日まで通してきたのだろうか。
同書149頁より引用
感想(ネタバレ有)
この話での主人公、勝呂は小心な男である。
その小心さは、医者には到底不似合いな性格である。
さて、その小心な男が、戦争という特殊な状況下であるからか、それとも医師という職業の業であるのか「患者を叩く」という行為を起こす。
「救いたい」「救ってやりたい」と思う気持ちの反面、自身の思い通りにならない患者への「面倒くささ」も抱えているのである。
救ってやらなければならない人間として見ていた患者を、いつしか「死ぬしかない」「医学の発展への犠牲」と徐々に考えていく勝呂。
そんな心の変化に自身で気が付きながら「神様とはあるのか」と勝呂は零す。
先述の通り、遠藤周作はキリスト教作家である。
「神なき国」日本で生きた、キリスト教作家なのである。
「隣人愛」「恩赦」「神様は乗り越えられる試練しか与えない」
等という言葉が思い浮かぶが、「海と毒薬」は神の言葉が生ぬるいほど残酷な現実を映し出している。
一見、西洋のキリスト教的教えへの皮肉のようで、キリスト神話の寛大さを表している。
勝呂やその他の医師・軍人は人の命を奪ったのに、まだ「生きている」のである。
まだ「生きている」ことは、神による恩赦なのか。償いなのか。
私には決めかねると感じました。
戦後を生きる勝呂は、感情描写が少なく、生きる屍のように生きている。
日常に起こる全ての感性や感情を感じないように生きている勝呂の切なさが、第三者「私」を通じありありと伝わってくるのである。
まるで目の前に出された食事を、味わうことなく咀嚼し、喉に押しとおすような日常を生きている。
第二次世界大戦、いえ「戦争」を語るには、私たちは深く終わりのない深淵を覗かねばなりません。
私たちだって今は生かされてされているけれど、遡ってみれば第二次世界大戦を引き起こした日本人の末裔なのです。
それをしばしば忘れたふりをして、私たちは生きています。
深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている、と言われますが、深淵の中にはあえて心を殺してでも覗かねばならないものがあります。
戦後の勝呂の姿は「覗かねばならない」という業を全うし続けている、尊敬すべき姿でもあるのだと私は感じました。
考えることは沢山ありますが、感想はこのくらいにしておきましょう。
是非、この作品を読んで、一緒に感想を語ってくれる方がいましたら歓迎いたします。
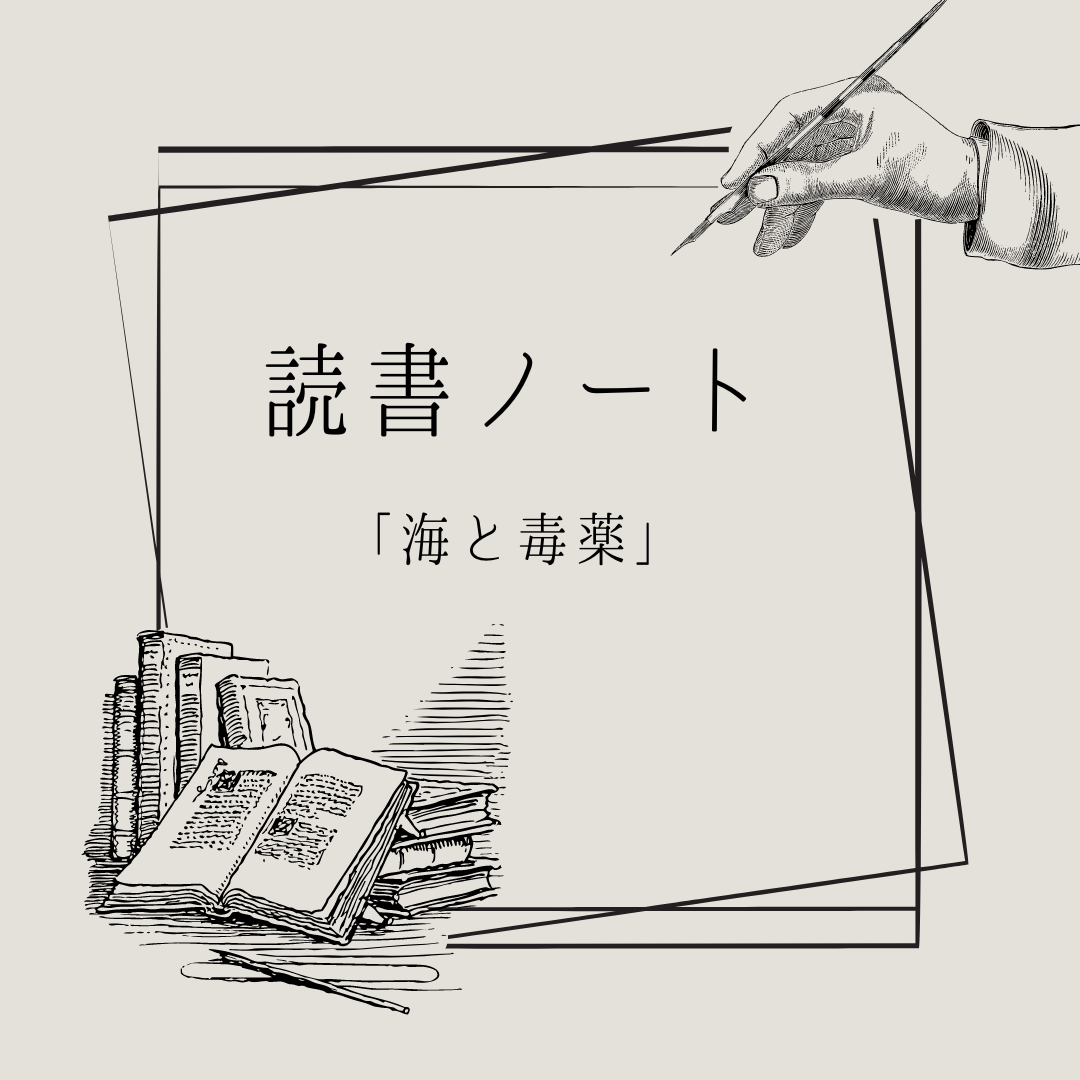


-120x68.png)
コメント