ダウンロード
「編む」
「これ、可愛い」
テーブルに並べられた色とりどりのアミグルミから一つを手に取った。赤い毛糸でつくられた鳥。丸い形に手触りの良い毛糸が肌に触れた。一つ一つの眼が均等に編まれた、丁寧な造り。
「二百円なんですよ。おひとつどうですか?」
テーブルの向こうから小学生くらいの女の子が声をかけてきた。その足元には丁度編んでいる途中の毛糸が転がっている。彼女は編む手を止めて、純粋な瞳でこちらを見つめていた。
「おひとつどうですか?」
小さな公民館で開催された町内バザーだった。近所に住む人たちが自分の特技を、その成果を持ち寄って展示したり販売したりする交流会のようなものだ。出店しているのは殆どがお爺ちゃんやお婆ちゃんと呼ばれる年代の人たちだ。周りの人たちに負けないくらいの商品を並べる彼女のテーブルは異質だった。
「ぜんぶ二百円です」
接客は得意ではないのだろう。テーブルの上には作品が並べられているだけ。彼女の接客は同じ文言を繰り返す。けれど気付けば二つ、手に持って購入していた。最初に取った赤い鳥とその対になるようなデザインの桃色の鳥。不慣れな手つきで彼女は袋に鳥を詰めていく。硬貨一枚を手渡して、お釣りを受け取った。
幸せそうに笑う「店員さん」だった。袋に入れる直前に鳥たちの頭を撫でていた。小さな声で、大事にしてもらってね、というのも聞こえた。袋に詰められた鳥たちは肩を寄せ合っていた。毛糸と綿でできた彼らは温かかった。
このバザーで売っているものは、お金を稼ぐためのものではない。そういう目的で出店している人たちはいるけれど、ほとんどは自分の作品を人に見せるための場として活用する。小さな店員さんのお店は後者だった。お財布からいなくなった一枚の硬貨と右手に持つ二羽の鳥は同じ。とても不思議な感覚だった。
昔、店員さんと同じくらいの年頃に私も編み物を習ったことがあった。祖母に教わりながら、マフラーをつくろうと思った。ところがこの祖母は偏屈な人だった。
「好きな毛糸を選びなさい」
手芸コーナーに連れていかれて、とてもわくわくしたのを覚えている。自分の伸長よりも高い棚に沢山の綺麗な毛糸が並べられていた。私は腕を伸ばして、ワインレッドの毛糸を手に取った。
赤が好きだった。ヒーローの色だ。アニメでさっそうと現れて困っている人を助ける、正義の色。私は女の子だ。だからヒーローにはなれない。ヒロインはピンクだった。
祖母の持つ店内カゴに毛糸を入れた。棒針を吟味していた祖母は毛糸を見て言った。
「色が古臭いんじゃないの。もっと可愛い色にしなさいよ」
祖母は毛糸を棚に戻してしまった。そうして桃色の毛糸がカゴに入ってしまった。納得がいかなくて、そっと桃色の毛糸をカゴから抜き出し、そうして今度は紅葉色の毛糸を入れた。ワインレッドの毛糸には手が届かなかった。祖母は目ざとく毛糸を棚に戻し桃色のものをカゴに戻した。
「あんた、本当は何色でもいいんでしょう? ならこの色にしなさい。可愛いわよ」
何色でもよかったわけではなかった。赤が良かったのだ。けれどお金を出してもらうから、教えてもらうからとそれ以上の抗議はできなかった。祖母はうきうきとレジに向かうが、私の足取りは重くなっていた。
帰宅後、母に一連の話をした。母は
「あんたがもっと上手に毛糸を編めるようになったら、赤い毛糸を買ってあげる。もしくは中学生になったら少しだけお小遣いをあげるからそれで買えばいいでしょう?」
と笑っていた。それなら、と桃色の毛糸でマフラーを編み始めた。なんども同じ作業を繰り返す。糸を絡めて針を抜いて、一段出来たら右手の針と左手の針とを交換する。小学生には編み物はまだ早いよ、と親戚から言われたけれど飽きることは無かった。周りの友達はゲームとかかけっことか、大人曰く子どもらしい遊びをしていた。私はどれも好きになれなくて、だから単純な作業を繰り返すと頭がすっきりした。親戚からの冷やかしとか宿題とか、嫌なことを忘れられた。家に帰ってすぐに宿題を終わらせて棒針に触る。手を動かしていても、頭で別のことを考えられる。ぐるぐるとこんがらがった思考の糸を一つ一つ丁寧に解くことが出来た。
マフラーも折り返し地点だったある夜のこと。続きは明日にしようとリビングのテーブルの上に編みかけのそれを置いてベッドに入り込んだ。ベッドの中はとても静かだった。隣の部屋からの大人たちの声が聞こえるほどに。酒を飲んで笑っている親戚の人たち、お酌をする母、仕事から帰ってきて呑みに混ざる父。
「まったく、やっぱり子どもに編み物なんかできるものじゃないね」
その声はまっすぐ耳に入ってきた。祖母の声だった。
「見てごらんよ、テーブルの上に編みかけを放置して。こりゃもうすぐ触らなくなるね。もう毛糸を買ってやってから二カ月経つってのに、これしか編めてないってことは飽きてるんだろうよ」
祖母の話は親戚の笑い声に混じっていた。いつもは気にせず眠れるはずなのに、その日は笑い声が耳に染みついて離れなかった。
「ここなんか編み目の大きさが違うじゃないか。こんな穴だらけのなんか誰が使うってんだ」
祖母のその言葉の後、どっと笑い声が大きくなった。世界で一人ぼっちになったような気持ちだった。暗い部屋の中、どれだけ布団にくるまっても笑い声は残り続けた。まるで壁や家具にぶつかって反響しているよう。緊張の糸が引っ張られて、それまで紡いできた期待だとか決意だとかが解かれていく。長い長い夜だった。
結局、マフラーは完成しなかった。編み途中だったそれをごみの入っていないごみ箱に入れた。見つけたのは祖母だった。祖母は編みかけの「それ」から針を引き抜いてしまった。母からは
「物を大切にしないならお小遣いの件も考え直さないとね」
といわれた。悲しそうな顔だった。祖母からも何か言われた気がするが、もう覚えていない。親戚も酒の肴にする中、父だけは何も言わなかった。
袋から二羽の鳥を放つ。今は一人暮らしのせまい家の棚の上に止まっている。その棚の一番下の段には、あの時の残りの毛糸が眠っていた。
沢山の大人たちの中で負けずと自分の作品を並べる店員さんは輝いて見えた。
あとがきに代えて
本作品は文学フリマ広島2023にて、ふみつづりの発行紙「ひみつきち」に掲載いたしました。
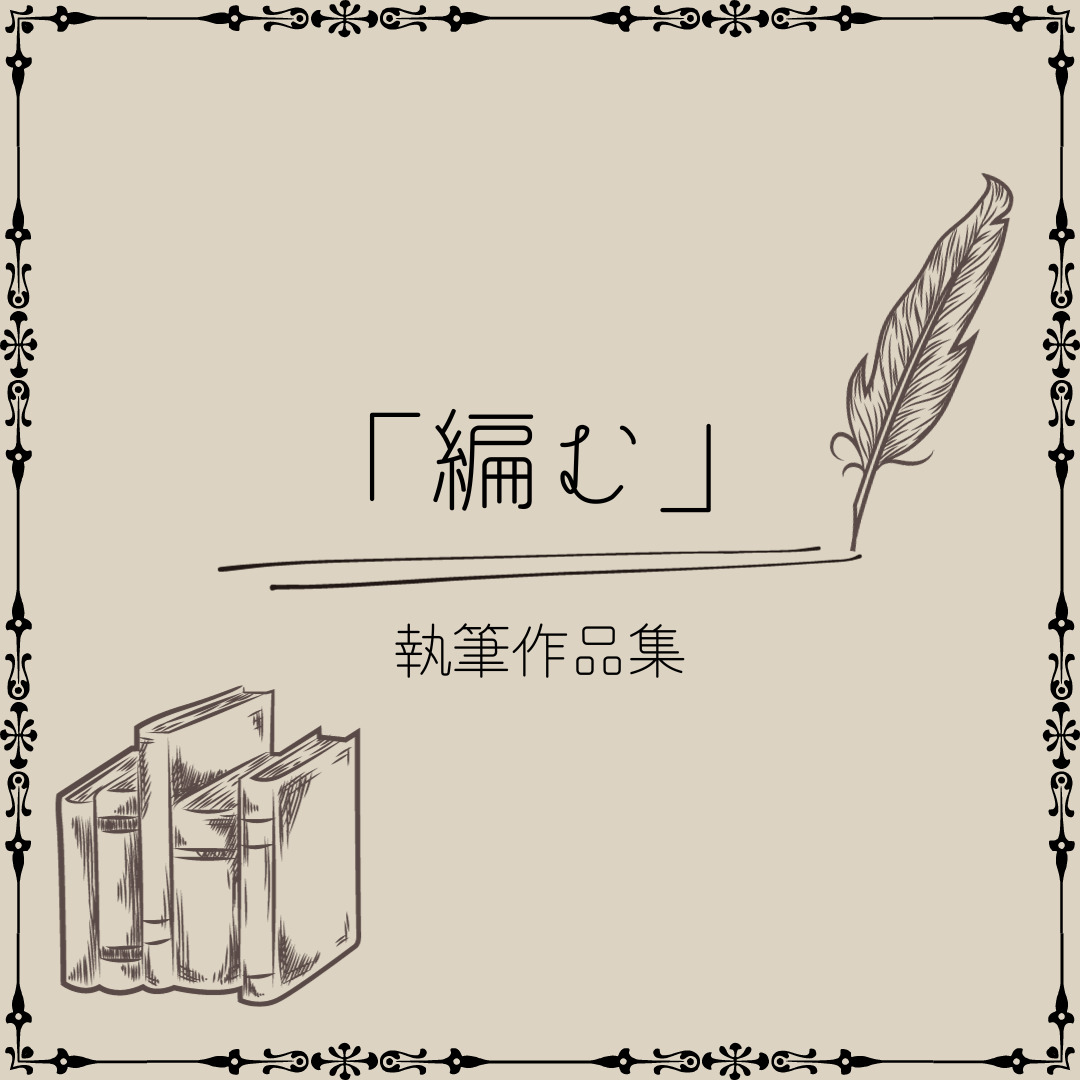


コメント