ダウンロード
本サイトに掲載している作品の無断複製、SNS・動画・その他サイトでの使用、自作発言等は禁止しています
本文
「ねぇ見てよ、この楽譜」
そう言って彼が取り出したのは真っ黒な革表紙の楽譜だった。魔導書みたいだろ? と、そんなものに憧れる彼を中二病のようだと思った。
「すごいよなぁ、こういうの。人には言えないけどさ憧れない?」
「お前、俺に話してるじゃんか」
「お前ならわかってくれると思ったんだよ」
彼はページをパラパラとめくった。
「どれでもいいからさ、一曲弾いてみない?」
彼はにやりと笑う。俺はたぶん頷いたのだと思う。けれどどんな顔をしていたのか、正確には覚えていない。
「雪村さん、この度は優勝おめでとうございます」
そういって記者はこちらに音声レコーダーを向けた。眩しいと顔を歪ませてしまうほどのフラッシュの中、目の前の記者は笑顔を張り付けたままだ。
「本当に素晴らしい演奏でした」
「ありがとうございます」
「荒々しく強烈で、叫んでいる、葛藤が響いてくるような演奏でした。身体の中にビリビリと電撃が走るようでしたよ」
「ありがとうございます。恐縮です」
「ところで、雪村さんにお聞きしたいことがありまして、前回の×××コンクールとは演奏がまた変化があったとお見受けします。何か心変わりなどがあったのでしょうか?」
俺は少しの間、口をつぐんだ。頭の中であの日の真っ白なカーテンが思い浮かんだ。その先には夏らしい水色の空があった。開いた窓から風が吹いて、あっという間に「彼」は消えてしまった。最後の瞬間にこちらに手を伸ばして、それが掴めずに泡となって消えてしまった。
「旧友に久しぶりに会ったんですよ、とても憧れていた友人だったんです」
「どのような方だったんですか? 憧れていたということはその方もピアノを弾かれていたのでしょうか?」
「……誰も知らない人ですよ」
真っ白なレースカーテンが揺れる。そこから差し込んだ光が棚にいくつも陳列されたトロフィーを照らす。どれも俺が持っているものよりも大きくて輝いている。磨き上げられた表面に反射する光が眩しくて仕方なかった。
「雪村、どれ弾く? あ、これとかいいんじゃない?」
彼は真っ白で透き通るような爪をタイトルに押し当てた。「声なき革命」。タイトルをなぞるとはっきりと彼の爪の後が神に残った。タイトルの横には人魚姫のイラストが描いてある。
「なんで人魚姫なんだよ」
「ほら、ここに『Wenn du spielst, wird dein Wunsch wahr』って書いてあるだろ。しかもこれだけ手書きで書き込まれてんの。ますます魔導書っぽくない?」
「RPGでも楽器弾いて魔法出すやつ居ないだろ」
「そうなの? ゲームやったことないから知らないや。でもかっこよくない?」
彼はこの部屋の真ん中に窮屈そうに据えられたピアノの前に立った。まるでこれからワルツを踊るかのように両手を広げた。ペアの相手を待つ女性のように指を鍵盤に向ける。目線が楽譜に向く。息を吸うと胸がわずかに盛り上がった。白鳥が地面にゆっくりと着地するように指先が置かれる。彼の白い指が鍵盤の白と混ざる。失恋した人魚姫が泡になるまで、静かに泣く歌。
何がここまで音を変えるのだろうか。同じように鍵盤を弾いているはずなのに、と思わされる。恐ろしいほどに繊細で消え入りそうな、しかし記憶に最も深く残る甘い音。音が響く。壁に、窓に、トロフィーに、そして俺の体に。この部屋全て支配する優しくて甘えた音。
唐突に彼は音を外した。
「ここが難しいや。うーん」
「あー」
「何、また発作?」
「うー、お前やっぱ嫌い」
彼は、またなのそれ? 、と言いながら笑っていた。もう何度も彼に面と向かって嫌いだと言い続けている。その度にのらりくらりと交わされ続け、最近では発作とまで言われるようになってしまった。
「嫌い、何でこんな綺麗に弾けんの。腹立つ」
「俺はお前が弾くの好きなんだけどなぁ」
「俺は嫌い。お前が弾く曲、全部嫌い、ぐううう」
「ほら、次、お前の番だよ」
楽譜を手渡された。渋々、ピアノの前に腰かける。彼の姿を思い浮かべながら、指を鍵盤に置く。
楽譜を見ながら、たどたどしく、間違えないように弾いていく。自分の弾いている音を聴きながら、やっぱり彼の音とは全然違うと嫌になってくる。稚拙に連なるだけの音だと悔しくなっていく。
目の前の彼が間違えたパートも何とか弾き切る。あと数小節。
彼は驚いたようにこちらを見つめ、お願い事をするように胸の前で手を結んでいた。白い肌に細く長い指だ。できることならば彼のような手になれたらよかったのに。
開け放たれた窓から生ぬるい空気が入り込んだ。額に汗が流れる。数秒遅れて、拍手の音が聞こえてくる。
「すごいね、一発で弾き切っちゃうなんて」
「お前みたいに弾けないから、弾き切るぐらいはしないと」
「すごいなぁ、ね、俺もう一回弾いてみようかなあ」
勝手にしろよ、とピアノから離れた。彼は先ほどよりも優雅に指を置く。弾き始める。先ほどと同じ場所で音を外す。彼はヘラヘラと笑っていた。その後も幾度となく音を外している。軽薄な笑顔に怒りが沸いてくる。もしかしてわざと間違えているんじゃないだろうか。
「ねぇ、難しいから一緒に弾こうよ」
「やだよ。お前なら弾けるだろ」
ちぇ、と言いながらまた冒頭を弾き始めた。今度は先ほどまで間違えていたところで躓かなかった。それが一層腹立たしかった。やればできるじゃんか、とすぐに口に出して演奏を止めてやりたかった。
「雪村! お願い、俺も弾けるようになったからさ。ね、ね、一緒に弾こうよ」
彼は胸元で手を合わせた。一つ溜息をついて、ピアノへ向かう。彼は長椅子から半身はみ出して座り直した。空いた場所へ腰を掛ける。ワクワクしたようにこちらを見つめている。頷いて合図を送った。
彼がもう一度鍵盤に指を下ろす、と同時に白いレースのカーテンが大きく膨らんだ。差し込んだ太陽の眩しさに思わず彼を見る。彼の手は鍵盤に触れたところから崩れて消えていた。
「あれ」
積み重ねられた紙の束が崩れるように、力が加えられた部分から手が解けていく。皮膚は白い紙切れのように細かくなっていく。体の内側から泡が溢れて、俺の目の前を通り割れて消えていく。
両腕が綺麗になくなった。そして肩から先もなくなろうとしている。呆気にとられた彼はこちらに顔を向けた。しょうがないな、と言いながら子どもをあやす様に顔を崩している。
「何呑気にしてるんだよ!」
宙に浮いて消えていく紙吹雪を掴もうと俺の腕を伸ばした。掴むために握った掌の風圧で紙はくるりと動きを変えてしまう。全くつかめない。目の前の彼が何かを言おうとした。声が出ていなかった。彼の喉から飛び出た泡を掴もうとまた腕を伸ばした。
瞬間、腕が焼けるように痛んだ。伸ばした腕を反射的に押えた。服をめくると二の腕に大きく赤黒い痣が出来ていた。
呼吸が早くなっていく。自分の胸が大きく膨らんでいるのがわかる。比べて彼はどんどんと小さくなっていく。最後の髪の毛一本が風でふわりと舞い上がった。そして弾けるように消えてしまった。ヒュッと下手な呼吸が自分の喉の奥から聞こえた。腕の痛みが強くなった。鍵盤に頭をのせる。音が鳴る。音が頭の中で反芻する。ピアノを中心に視界がグルグルと歪んでいく。太陽光を反射したトロフィーの輝きも鍵盤の白さも全てがただの光の線へと変わっていった。そうして上がってくる吐き気から逃れるように目を閉じた。
しばらくして起き上がったのは自分の部屋だった。先ほどまでの吐き気や倦怠感もなくなっていた。不思議な夢を見ていたような気分だった。
「アンタ、倒れたんだってね。学校から連絡あったわよ」
視界の端で母親が言った。まだ視界がぼやけていた。そのまま腕に目を向けると、惨たらしい大きな痣が見えた。
「ねぇ、学校で何かあったの? こんなところに怪我して」
母は心配そうにこちらを見つめている。そういえば、学校にいたのだろうか。いや、目を瞑れば彼を取り巻くトロフィーと青く眩しい空と白いカーテンが見えた。先ほどまでいたのは彼の部屋だったはずだ。母の顔を見る。少しだけ目を潤ませている。
その部屋の奥に鈍い埃をかぶった、見覚えのある形のトロフィーが見えた。
「母さん、あのトロフィーって誰の……?」
「……なに、どうしたのよ。あれはこの前、アンタがコンクールで貰ったものでしょう」
布団を蹴り上げた。急いで状態を起こしたためか、腕が重く痛みを主張した。急いでトロフィーに駆け寄る。受賞者の欄には俺の名前が彫られていた。
遠くから低いピアノの音が聞こえた。頭痛。吐き気。先ほどまでの光景が脳裏によぎる。頭の奥、正確に言えば耳の奥を何かが移動するように痒くなった。
「俺はこれ取ってない」
「本当にどうしたの、わかったから、安静にしていなさい」
「これを取ったのは、アイツなんだ」
「アイツって……誰のこと言ってるのよ」
「アイツは、あれ、名前」
消えていく横顔も、彼の演奏も、醜い嫉妬も全て鮮明に覚えていた。けれど名前が出てこなかった。先ほどまでいたはずの部屋、彼の家の場所も分からなくなっていた。
母の手を借りてピアノの前まで腰掛ける。なぜか今、無性にピアノが弾きたかった。彼の演奏を忘れないように、真似したくなった。左手で、左目を押えながら、右手で鍵盤に触れる。彼はこんな無様な演奏はしなかっただろうと思いながら、ドの音に体重をかけた。
驚くほどに繊細な音が鳴った。いつも通り引いたはずだった。今奏でているピアノの音がノイズを打ち消すように頭痛が治まっていく。
体の動くままに鍵盤に触れる。音が清々しく聞こえている。信じられないほどに切なく、甘ったるい音が身体に響いた。
「この腕は、アイツの腕なんだ」
じっと手のひらを見つめた。
もう誰も彼の演奏を覚えていなかった。それどころか彼の物だった全てが俺の物へと置き換わっていた。これまで取った賞状、トロフィーも、実直で奥ゆかしい演奏も……その後に得られたはずの賞賛も全て俺の物になった。
……賞を取れたらもっと嬉しいものだと思っていた。褒められたら舞い上がるものだと思っていた。けれども罪悪感ばかりが膨らんでいった。黒革の楽譜に書かれていた走り書き『Wenn du spielst, wird dein Wunsch wahr』は、弾けば願いのままに、という意味だった。
「あの時、俺はお前の手が欲しいと願ったから?」
まさかそんなことあるわけがない、と思いながらもあの日の夢のような出来事を鮮明に思い出すことができた。
罪悪感からピアノを弾き続けていた。使命だった。彼の演奏をなくさないために、弾き続けなければならないと思った。白い鍵盤が黒く濁って見えるほど、演奏はいつも吐き気がした。
次第にコンクールやコンテスト、発表会であらぬミスを連発するようになった。その度に二の腕の痣が鈍痛を引き起こした。この痣はいつまで経っても治ることは無かった。
「天才と呼ばれた雪村も、ここまでかな」
誰かの言った声が聞こえてきた。これは俺の才能じゃないと叫びたかった。演奏をするたびに、彼ならもっと上手く弾いただろうと思い知らされていく。彼の演奏は彼の人生に裏打ちされてこそ輝いていた。
演奏なんてやめてしまいたい。自暴自棄になっていく。二の腕が尚も強く傷む。肉が骨から剥がされそうなほど、何かにつままれている感覚。ほらまた、青黒くなっている。
もう黒鍵と白鍵の区別もつかない。自身の指でさえ、揺れて見える。大きな音を立てて楽譜が落ちた。あの日の黒革の楽譜だった。
盗人猛々しいとは俺のこと。彼の演奏をなくしてはいけないと考えながら、才能を彼に返すつもりはなかった。罪悪感と言いながら、賞賛に安堵する気持ちもあった。「声なき革命」のページを開く。あの日のまま、『Wenn du spielst, wird dein Wunsch wahr』の文字が眼に入る。
もう一度弾く。彼がやっていたように、鍵盤に触れる。最初の音を鳴らす。ふとどこからか彼が見ているような気がした。もう一度、奪ってしまった彼の場所を、返したいと願った。
右手に何かが乗った。音が軽く無くなっていく。元の嫌いな俺の演奏に戻っていく。楽譜から右手に目を向ける。白く透き通るような手が右手に乗っている。
(止めないで)
右側から、ピアノの音に重なって彼の声が微かに聞こえる。
(ずっと待ってた。やっと願いが叶うんだ。だから止めないで)
驚いて危うく音を外しかけた。止めるな、と彼は何度も囁き続ける。
(お前の楽譜になりたいと思ってた。楽譜になりたいなんて、おかしなことかもしれないけれど、雪村の演奏で俺の気持ちが代弁されたらどんなに嬉しいだろうと思ってた)
「恨んでないのか」
視界の端で、彼は横に首を振った。笑っているような気もする。
(初めて演奏を聞いた時、耳の奥まで音が入ってきて、なんて激しい乱暴な音だろうと思った。父さんは雪村の演奏は好みじゃなかったんだって。散々比較された。でも俺は支配の無い場所で自由に踊るように弾ける演奏が羨ましくて仕方なかった)
彼の手を見る。彼はずっと長袖を着て隠していた。手の先、爪は長く伸びていた。彼なりの、ピアノへの声なき革命だった。
(ピアノなんか楽しくない。俺も俺の演奏が嫌いだ。間違えないように精一杯で、怖がってばかり。でも雪村みたいに弾けたらきっと楽しい。雪村と弾けたらもっと楽しい。だから雪村が弾く曲の楽譜になりたいと思った。俺はきっと雪村の演奏を邪魔してしまうから、それでも二人で音を弾きたかったから)
その言葉を聞いて、ピアノから手を離した。最後の音が反響する。ようやく隣をしっかり見られた。あの日の学生服のまま、彼は驚いた顔をしていた。
(なんで止めるの)
「……願い事を間違えた」
楽譜のページを一番最初に戻す。タイトル下の文字が変わっている。「Genau wie du」。もう願いは叶わないのかもしれない。
「お前も弾けよ、一緒に弾くんだろ」
そう言って椅子を半分空ける。音を止めると彼の姿は見えなくなった。けれども彼の体を通り抜ける風が生ぬるいから、彼が隣に座ったことがわかる。彼だけはあの夏の日のままなのだ。
「楽譜がデュエットじゃないからな、俺がオクターブずらすぞ」
返事のないまま、指を走らせていく。鍵盤に二人分の体重が加わった。
彼が奏でているためか、俺の演奏は昔のような、荒くれた、暗い音を響かせた。デュエットの主役だと言いたげに隣からは澄み切った音が聞こえてくる。ピアノが、部屋が、楽譜が喜んでいるかのように、響き震えている。足の裏から、二人で奏でた音の振動が伝わってくる。鍵盤が力を持っているかのように、指を押し出し、次の鍵盤へ運んでくれる。俺の体が揺れているのがわかった。そして恐らく彼の体も揺れている。生暖かい風が首元や頬に当たる。二人なら怖くない、そんな安心感が身体を包む。包み込む熱が隣からも伝わってくる。
願いを指先に込める。音に込める力が強くなっていく。二人の指先が鍵盤の上で踊る。彼の指先と俺の指先が重なっていく。
沢山のフラッシュライトに目が眩しくなった。
「旧友に久しぶりに会ったんですよ、とても憧れていた友人だったんです」
「どのような方だったんですか? 憧れていたということはその方もピアノを弾かれていたのでしょうか?」
「……誰も知らない人ですよ」
これ以上語るつもりがないことがわかると、記者は残念だと口を尖らせていた。不意に背中を誰かが撫でたような気がした。生ぬるい風が当たっただけかもしれない。もう腕の痛みはなくなっていた。

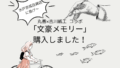

コメント