ダウンロード
本サイトに掲載している作品の無断複製、SNS・動画・その他サイトでの使用、自作発言等は禁止しています
本文
平成二十二年の十円玉が二枚、昭和五十年の五十円玉が一枚、机の上に乗っていた。これが今の所持金だった。最後にご飯を食べたのは昨日のお昼。空腹でお腹が鳴るけれど、鳴っているうちはまだ何とか生きられる。棚を漁って、湿気った煎餅の残骸をかじる。何度見つめても机の上の金額は変わらない。
「とりあえず母さんに電話してみようかな……」
七十円を握り締める。家の電話はもうどこにもつながらない。
一週間前に母の置いていったお金で、コンビニでご飯を買った。残り七十円。もしも母が帰ってきたら、計画的にお金を使いなさいと一発殴られるかもしれない。殴られても良いから、今日はご飯が食べたかった。カレンダーに丸印がついている日だから。
ドアを開けると部屋の中よりも明るい闇が、足元に転がり込んでくる。夜闇、街灯の明かりを目ざして、公衆電話に向かう。その途中には大きな神社があって、夜だと少し怖い。何を思ったのか、十円玉の内、一枚をお賽銭箱に入れようと思った。電話をかけても、きっと母は出てくれないから。そんな母の気持ちを電話を掛けた刹那だけでも変えてくれるんじゃないかと希望が欲しかった。
暗がりの中でポケットをまさぐってお金を一枚入れる。木と金属がぶつかって、カランコロンと体中に音が響く。大人の人に見つかったら、連れていかれてしまうから神社の鐘は鳴らせなかった。
「神様、どうかお母さんが電話に出てくれますように」
手を合わせて祈る。同じくらいの歳の子たちがこうやってお祈りしているのを何度か見たことがあった。母はそんな子どもたちを鼻で笑っていた。そんなことしたって、神様なんていやしないのに、と。
いきはよいよい、かえりはこわい。そんな神社から公衆電話へ向かう。少しばかり高い位置にある、重い受話器を耳に当てて、ポケットに手を入れる。お金を二枚取り出す。白い手に載ったのは茶色い二枚の硬貨。
「間違えて五十円玉を入れちゃったんだ」
二十円で母が話を聞いてくれるだろうか、嫌な不安が膨らんだ。後戻りはできず、震える手でボタンを押す。プルプルと聞き覚えのある音が鳴り、知らない男性の声がした。母の名前を告げると、やがてワントーン声の高い母が挨拶をする。
「はーい、どちら様です?」
「あの、その電話かけてごめんなさい」
名乗りはしなかったが、電話をかけてきた相手がだれかわかったのか、母は大きなため息を吐いた。それから、電話の向こうにいる「友人」に、ちょっと電話かけてくるね、と告げた後、不機嫌そうな声色で電話に戻ってきた。
「なに」
もう一枚、お金を入れた。早く言わなければ、と焦る。
「電話してごめんなさい、次帰ってくるのいつですか」
「しばらく帰れないんだけど……まさかお金もう無いの」
「ごめんなさい」
「あっそう、うーん、次お金送れるのいつになるかわからないけど、早めに出すわ」
「ごめんなさい、ありが……」
言葉の途中で電話は途切れてしまった。感謝を伝えられなかったので、もしかすると、お金がくるのは作になってしまうかもしれない。お金がない不甲斐なさと恥ずかしさで、顔が熱かった。どこかぼうっともする。文字通りの一文無し、何処にも寄り道をせずに真っ直ぐ家へ帰った。行きに怖かった神社も、もう怖くなくなってしまった。
アパートの扉を開けるとむわっとした、酸っぱい匂いが足の間を通り抜けた。ずっと家にいる時がつかないけれど、もう風呂に入らないで数日たっているのだ。明日は公園で水を汲んで来ようと、玄関に無造作に放り投げられた風呂桶を見る。その奥にぼんやりと白い影が見えた。家を出てくるまで無かったものだ。人間のようだけれど、人間は発光しない。おまけに背中に真っ黒な羽もある。
「きみはだれ?」
それはヒト型をしていた。呼びかけると、呼びかける前よりもしっかりと表情がわかるようになった。眉間に皺を寄せて、口を真一文字に結んでいる。
「お前、こんな家にいて臭くないのか」
「……やっぱり臭いかな、明日水汲んでくるから少し待っててよ」
呼びかけを続けると、目の前の彼は驚いたように目線をこちらに向けた。
「家に知らないやつが入って来てるのに、怖がらないのか」
「怖がらないよ、前もよく居たし」
もう随分と前から、玄関の鍵は閉めていない。その方が人が遊びに来るからだ。遊びに来ると言っても少し前のことで、最近はもう誰も来なくなってしまった。
「ふーん、でも困るだろ、何か盗まれたりしたら」
「食べ物盗まれたら困るけど、今はお煎餅しかないし」
湿気った煎餅の袋を見せると、彼はその袋を睨みつけた。そして溜息をついた。なんだか溜息をつかれてばかりだなと胸が痛くなった。
「俺はシキ。神様見習いなんだ。お前の願いをかなえてやるよ」
「……」
「なんか言えよ」
「いや、何かどこかで読んだようなセリフだなと思って」
シキと名乗る彼は腕を組んで怒りを表した。
「なんだよ、お前が神社に賽銭入れたから来たんじゃないか」
「え、そうなの。僕間違えて五十円玉入れちゃったんだよなぁ」
「はぁ? それで俺はこんなところに駆り出されたのか」
「こんなところとは失礼な」
シキの周りは洗っていない衣服でいっぱいだった。水が止まっているから、当然洗濯もできない。明日、水を汲んできたなら、服も洗わなければいけない。
「……五十円入れたなら、あと四つは願いを叶えられるな」
シキは指折り数えて告げた。
「なんであと四つ?」
「さっき、母親がちゃんと電話に出ただろ。」
母親が出る前に電話が切れる可能性もあったんだぜ、とシキは笑った。
「本当に君の力なの?」
電話くらいタイミングと母の気分次第で出てくれる気がしていた。それをシキの力で捻じ曲げたというには信用が出来なかった。
「じゃあ、試しに願い事をしてみろよ。一回減るけど、ちゃんとかなえてやるよ」
しばらく悩んでから、ふとカレンダーが目に付いた。今日の日付には丸がついている。
「……例えばこの家を掃除できたりする?」
「おうよ、そんなことでいいのか」
シキが右手の人差し指をたてた。そうして宙に円を書くように回す。するとシキの指の動きに合わせて部屋中の物が移動し始めた。落ちて、積み重なったカップ麺の皿はゴミ袋に入った。散乱していた洗っていない服も、シキの指から湧き出た水で洗われ、全てハンガーにかけられた。窓が開き、風が通り抜ける。先ほどまでの酸っぱい匂いではなく、木材の温かな香りが身を包んだ。
シキは満足そうにこちらを向いた。ずっとへの字だった口がにっこりと笑うほどだ。
「どうだ、俺の力、すごいだろ」
部屋は見違えるほどに綺麗になっていた。床にはもう何も落ちていない。初めてこの部屋に、母と来た時のように、綺麗だった。
「これで母さんが帰って来ても怒らないや」
「……さあ、次のお願いはどうする?」
「えーっとね、ぼく、お風呂に入りたいんだけど」
この部屋に不釣り合いなほど、体が汚れているのが理解できてしまった。恥ずかしくて、一刻も早く自分の体をなんとかしたくなった。
「じゃあ、お金やるから銭湯行ってこいよ」
「え、さっきまで魔法使ってくれてたのに、いきなり雑じゃない?」
「しょうがないだろ、力使ったら疲れたんだよ。こんだけ綺麗になったんだぞ」
「じゃあ、一緒に銭湯? に行ってよ」
シキは二回分のお願いな、と言って手を引いた。一つ瞬きをすると、彼は人間の姿になっていた。黒い羽も神々しい光もない。少しばかり自分よりも大きな体をしていた。強引に、けれどもがっしりとした安定感で銭湯までの道、手を引かれた。
シキを見ながら銭湯に入る作法を真似した。体を洗って湯船に浸かる。足を伸ばしてお湯に入るのは初めてだった。シキは一度ぼくの体を見てから、困ったように笑った。
「気持ちいいか」
「うん、ちょっとくらくらするけど」
「……次のお願いはどうする?」
しばらく考え込んでから、家に帰ってからお願いするというと、彼は頷いた。先ほどよりももっとずっと目が回るようになってきた。シキはまた強い力で手を引いて湯船から外へ連れ出してくれた。
「サービスだぞ、神様に言ったら怒られちゃうんだからな」
そう言いながら温泉饅頭を手に握らせてくれた。帰り道もシキは手を繋いでくれた。夜道を歩くのはもうずっと昔から怖くなかった。けれども今日はドキドキして、冒険のようで、怖さと楽しさが湧いてくるようだった。シキの後姿を見ながら、お兄ちゃんみたいだなと思った。
家に着くなり、シキは時計を見て言った。
「さあ、最後のお願いはどうする?」
だからもう一度、カレンダーを見た。
「今日、僕が生まれた日なんだって。むかし母さんに言われた。だからケーキが食べたい」
ケーキを食べるなら、綺麗な部屋で、綺麗な体で食べたかった。そしてできることなら、誰かとケーキが食べて見たかった。
この部屋に人が来ていたのは随分前のこと。そして彼らが家に来なくなったのは、この部屋が汚いからだった。もしも綺麗になったらまた人が遊びに来てくれるかもしれない。そうでなくても、今はシキが目の前にいる。
シキは頷いて、指を振った。すると大きな白いケーキが出てきた。イチゴが輪っかを作るようにぐるりと並んでいて、その中心にはチョコレートプレートが並んでいる。
「あれ、僕の名前、教えたんだっけ」
「俺は神様見習いだぞ。お前の名前くらい知ってる」
さあ食べろよ、と言わんばかりに、シキはフォークを手渡した。一緒に食べてよ、というと嬉しそうにしょうがないな、と彼は言った。初めてのケーキ、空腹もあって本当においしかった。
「お前誕生日なんだろう、じゃあ特別に、もう一個だけお願い事しろよ」
「かなえてくれるの?」
「特別だぞ、サービスだ」
シキはまっすぐ僕の目を見ていた。家族がいたら、兄弟がいたらこんな感じだったんだろうか。
「じゃあ、全部、無かったことにして」
シキの嬉しそうな顔が崩れるのはあっという間だった。なんで、どうして、と彼は続ける。先ほどまで笑っていた顔が一気に強張った。口が真一文字に結ばれた。
「知ってるんだ。神様なんていないよ。いたとしても、僕だけをこんなに特別に扱ってくれるわけがないって」
「良いじゃないか、今まで耐えてきたんだ。今日はお前の誕生日なんだろう」
「うん、でももう幸せな気持ちにさせてもらったから十分。僕に漬かった願いの分、母さんや友達や、もしかしたらどこかにいるかもしれない父さんとか、いろんな人にあげてよ」
そう言葉にしながら何だか泣きそうになっていた。幸せな気持ちが無かったことにあるのが怖かった。けれどもこんなに良いことがあって、幸せな気分にしてもらえて、この後に来るかもしれない大きな不幸の方が恐ろしかった。幸せの後には必ず不幸がやってくる、母さんは何度もそう言っていたから。
「神様が僕だけに優しいなんてありえないんだ。僕だけが幸せになっちゃいけないんだよ」
「意志は固いんだな」
シキはヒト型をやめて、大きな黒い羽を広げた。カラスのよう。部屋の電灯に照らされて青く、月明かりを反射して虹色に光る。シキは泣きながら指を振るった。片づけられていた部屋も洗われた服も何もかもが元通りになっていく。これでいいんだと安心する。
「……嘘を吐いたんだ。電話と銭湯は俺の力じゃない。だからあと一回分、お願いできる」
力を振るいながら、シキは尋ねた。元に戻っていく感覚で頭がさらにぼうっとしてきた。さっきあんなにケーキを食べたのに、と思いながら腹が減るのを感じた。身体に力が入らなくなって立っていられなくなった。電話まで行って帰ってきたからだろうか、もう立ち上がる気力もなかった。凄まじい吐き気がして横になる。辛うじて開いていた右目で部屋を見る。一つの白い影が映る。人間のようだけれど、人間は発光しない。おまけに背中に真っ黒な羽もある。きっと人間じゃないのだろう。神様なのかもしれない。
彼は僕の名前を呼んでいた。何度も、何度も。僕の手を彼は強く握っていた。僕の手は彼の手に比べたら半分ぐらいの細さだった。彼はまだ名前を呼ぶ。泣きそうな、もしかしたら泣いているのかもしれない彼の顔を見ていたら、名前を呼ばれるのが申し訳なくなった。彼は神様じゃないのかもしれない。神様だったらきっと、僕だけを特別扱いしてくれることなんてないはずだもの。空腹と喉の渇きで、声のでなくなった口を開いた。
「どうか、もう……」

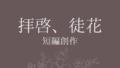
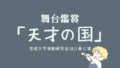
コメント