ダウンロード
本サイトに掲載している作品の無断複製、SNS・動画・その他サイトでの使用、自作発言等は禁止しています。
本文
しとしと雨が降る中、一人の貧しそうな女性が私が勤める古本屋にやってきた。時間は午前中だったように記憶している。彼女は傘を持っていなかった。古びた表紙の本を一冊手にして、濡れ乱れた服と髪を直そうともせず、消え入りそうな声で言った。
「買取をおねがいします」
服の首元、虫が食ったように小さな穴が開いていた。本を差し出す手の甲は乾燥に負けてあかぎれていた。随分とみすぼらしい。
本を売りに来るような人の多くは貧しい人だ。本人確認書類が免許証ではなく、生活保護受給証ということもざらにある。だから、けっして珍しいことではない。けれども彼女は、そんな「いつもの」人たちとは違い、肌は綺麗で鼻が高く、異彩な顔立ちをしていたように記憶している。私の記憶が、最初の出会いを後から塗り替えたのかもしれないが。
「免許証などはお持ちですか」
そう尋ねると、彼女は一瞬間だけ私の目を捉え、そうしてすぐに逸らしてしまった。一瞬であったが綺麗な琥珀色が光を以て反射した。しかしそれ以降はまるで今見えている世界の一枚奥を見つめるように暗い瞳であった。
「どうだったでしょう、ちょっと今日は持ち合わせていないかもしれません」
「そうなると、買取は厳しいのですが……査定だけでしたら」
彼女は頷いた。手渡された本を開いて状態を確認する。天井はかなり日焼けていた。カバーもボロボロで、下手に触れば破れがより一層ひどくなってしまいそうだった。じめじめと雨の香りが充満するこの季節では紙が余計に柔らかくなってしまう。幸いにして中に開き癖などはなく、何とか文字は読めそうであった。
「申し訳ないですが、ウチで買い取るなら十円といったところでしょうか」
査定の間、行き場なく書架をさまよう彼女に声をかけた。悩んだそぶりもなく、彼女は
「それで大丈夫です」
と言った。本の状態が厳しいこともあり、持ち帰らずにここに本を置いておくことになった。彼女の連絡先を受け取り、預かった本に挟む。居心地が悪そうに、カウンターの前で私の一挙手一等足を眺めていた。
「もう、大丈夫ですよ。明日お待ちしていますね」
そう声をかけると、彼女は荷物をまとめ始めた。その直後、とてつもなく大きな腹の虫が狭い店内に鳴り響いた。それは彼女の痩せた腹から聞こえてくるようだった。私は呆気に取られてしまったが、彼女は恥ずかしそうに頬を赤く染めた。この時、彼女は初めて表情という表情を見せた。
「……受付、終わった方に飴を差し上げてるんです。おひとついかがですか」
おずおずと彼女は手を伸ばした。そうして包みを割いて口に一つ頬張る。この飴は店に訪れた子ども用に置いてあったものだけれど、なんとも彼女の背中から漂う切なさに、口をついて出てしまったのだった。飴をからころと頬の中で転がす彼女は、口を右手で隠しながら言った。
「さっきのような本が家に沢山あるんです。私一人しかおりませんので、少しずつですが、また持ってきてもいいでしょうか」
私はにっこりと営業慣れした笑顔を浮かべて、身分証明書をお忘れなく、と付け加えた。
翌日も彼女はやってきた。先日と似たような服装で、その手には二冊の本があった。
「身分証は学生証でもいいでしょうか」
そう言って彼女が見せてきた学生証は、数年前で期限が切れていた。
「ほんとうだったら期限切れはダメですけど……ウチは小さな店ですし、良いですよ」
彼女は小さく微笑んでいた。
新しく持ってきた二冊の本の査定が終わるまで、彼女はまた書架の間をさまよっていた。やがて一冊の絵本を見つけ、ある一ページの絵に食い入るように長いこと見つめていた。
「査定、終わりましたよ」
そう声をかけると、彼女はゆっくりと顔をあげた。乱れたままの髪を耳に掛け、こちらを見つめる瞳はまた黄金色に輝いた。
さほど高くない金額に、彼女は文句もつけずに、手際よくお金をしまっていく。そうして今度は目をこちらに合わせ
「今日も……飴を貰ってもいいですか」
と、恥ずかしそうに聞いてきた。しまったことになったな、と心の中で思いつつも、どうぞ、と口角をあげて言葉に放つ。彼女はまたもその場で包みを割いて、口に一つ含んだ。店から出ていくとき、膨らんだ頬と口元を手で隠しながら丁重にお辞儀をしていった。
あくる日から彼女は本を持ってきた。多い日には五冊ほどを胸に抱いて。どの本も古びていて、日焼けが酷かったり、破れが酷かったりで大金がつくことは無かった。けれども不思議なことに、中の文字には浸食なく、読む分には差し支えないものだった。
査定の間、彼女はやっぱり棚から絵本を取り出して読んでいた。そうして彼女にとってお気に入りの絵が見つかると、声をかけるまで動かないのである。良く晴れた日は、薄暗い店内にも明かりが差し込む。レースカーテン越しに照らされた彼女は襤褸に包まれていようと凛とした一人の女性であると私には感じられた。
「査定が終わりましたよ」
そう告げると彼女は顔をあげる。もう何度目かになると、慣れたようにこちらに視線を運び、元あった場所に絵本を戻し、真っ直ぐにカウンターまで歩いてくる。
「……随分、古い本ばかりをお持ちなんですね」
客に対してこのように話しかけることは、本来慎むべきである。彼女はじっと私の目を見つめてから、そうして目を伏せ、髪を耳に掛けた。
「本は全て主人のものです。私は本なんて全く読みません」
初めて来店した時と変わり、その言葉は力強く聞こえた。なるほど、道理で、と心の中で納得した。彼女の開いていた絵本、開いていたページはどれも色彩豊かで、繊細な絵が描かれていた。彼女は文章ではなく、絵に心惹かれていたのだ。
その日の金額は、初めて四桁の値がついた。彼女は驚いていた。
彼女はそれから、少しばかり不定期に本を持ってくるようになった。そして漸く見つかったのだと、身分証に運転免許証を差し出すようになった。
「主人がね、私の免許証を栞代わりにしていたみたいなんです。パラパラめくってみたら、偶々」
そう言いながら彼女は苦笑していた。あの人はリスみたいに本の中にいろんなものを挟んでるんですよ、と続けた。査定が終わるまで、彼女が手に取る本は段々と文量が増えていった。絵本が児童書になり、それがやがて詩歌集に。それから短編小説へと変わっていった。古本屋に勤める人間として、こうやって本を読むようになっていくんだと、観察するのは少々の興味が湧いた。
彼女は「主人の本」をいくらか嗜んでから持ってくるようになったそうだ。しかし古い本ばかりということもあり、冒頭だけを読んで閉じてしまうことの方が多いらしい。買い取る本が増えるほどに、些細な会話は少しずつ積もっていった。
「本を読むってすごいのね、すっきりするような気がする」
彼女はそう言いながら、よく笑うようになった。乱れていた髪は整えられていった。光に美しく照りかえる黒髪だった。痩せ気味だった彼女の頬には程よい肉がつき、笑うたびに丸い頬袋が浮かぶようになった。貧乏臭かった服も次第に白いシャツや風になびくレーススカートへと変わっていった。
「査定が終わりましたよ」
その言葉に慣れた所作でカウンターまで戻ってくる。そうして出された金額を確認するために頭を下げる。結びから零れた髪を耳に掛ける。髪はさらさらとしていて、少しの動きで耳から落ちてしまう。
ある時から彼女は金額の端数分を募金箱に入れるようになった。カウンターの横においてある小さな募金箱。入れながら彼女は、細かいと計算が面倒なの、と零した。その表情には哀愁が漂うようで、地獄に蜘蛛の糸を垂らすような慈愛を伴っていた。
それからハッとしたように、カウンターに置かれた飴の籠を見た。
「そういえば、私、とてもみっともないことをしてしまったわね。この飴、ほんとうは子ども用だったんでしょう」
彼女はそう言いながら笑った。日輪花のように。
それからの会計後は少しばかり、お互いの身の上話をするようになった。彼女は仕事を始めたらしい。いつも旦那の愚痴を、笑って零すのだった。言葉とは正反対に、誇らしいような、愛おしいような、困ったように照れるのである。
私の人間観察はいつしか「心惹かれる」と言った方が正しいような気がしていた。不思議なことに誰かに想いを寄せる人間は魅力的に映る。彼女が査定待ちの間に本を読むしぐさは、薄暗い部屋に光を与えるようだった。写真に収められたように殆ど動かない彼女。その姿は言い表す言葉を持ち合わせないほどに美しかった。
ある夏の日。それは珍しくも夕暮れに彼女が本を持ってきた日だった。
「今日で家にある本はすべて持ってきたの」
そう言いながら寂しそうな表情を彼女は作った。私も同じような顔をしていたことだろう。彼女の爪は綺麗に彩られていた。服は上質なワンピース。少し高めのヒールをはいて、店内にコツコツと存在を主張する。
査定が終わるまでの間、彼女は一冊の本の表紙をじっと見つめていた。
「査定が終わりましたよ」
私の言葉に、彼女はその本を手にしたままカウンターへやってきた。そうして、差し引きでこの本を買わせてほしい、と申し出る。
包装されたその本を大事そうに彼女は手提げかばんに仕舞った。これから仕事に行くのよ、と彼女は笑った。その日の彼女は雄弁であった。
「主人はね、少し前に亡くなったのよ」
そんな言葉から最後の会話が始まった。
「借金もあって、生活もうまくいかなくって。突き動かされるように、すこしでもお金を作らなくっちゃと、主人が溜め込んでいたものを手放す毎日でした。でもね、手放したら今度は惜しくなる。あらゆる物に主人の思い出があって、あの人の魂があるようで。苦手だった本を読んだり、知らないことを知ろうとしたり」
一息、ため息を吐いた。それは身体の中の未練の残滓を綺麗に吐き出すようなものだった。他愛なく吐き出されたそれは、本当に小さなものだった。そうして彼女は、肺の中の空気を入れ替えるように、深く息を吸った。吸い込んだ酸素が血を通って、全身に巡るのを待つようにしばしの沈黙があった。
「……でもだめね、残された本に、魂なんて、これっぽっちもなかったもの」
心残りは無いようだった。改めて丁重にお辞儀をする彼女。もうカウンターで飴をねだる姿はない。店の外に立つ彼女は華やかで美しい女性だった。シンデレラのように貧しさに塗れていた人はどこにもいない。彼女の体のどこにも、もう主人の魂は残されていない。彼女は一人で歩いていくだろう。
彼女はもうやってこない。彼女はこの店の常連だった。
あとがき
とくになし
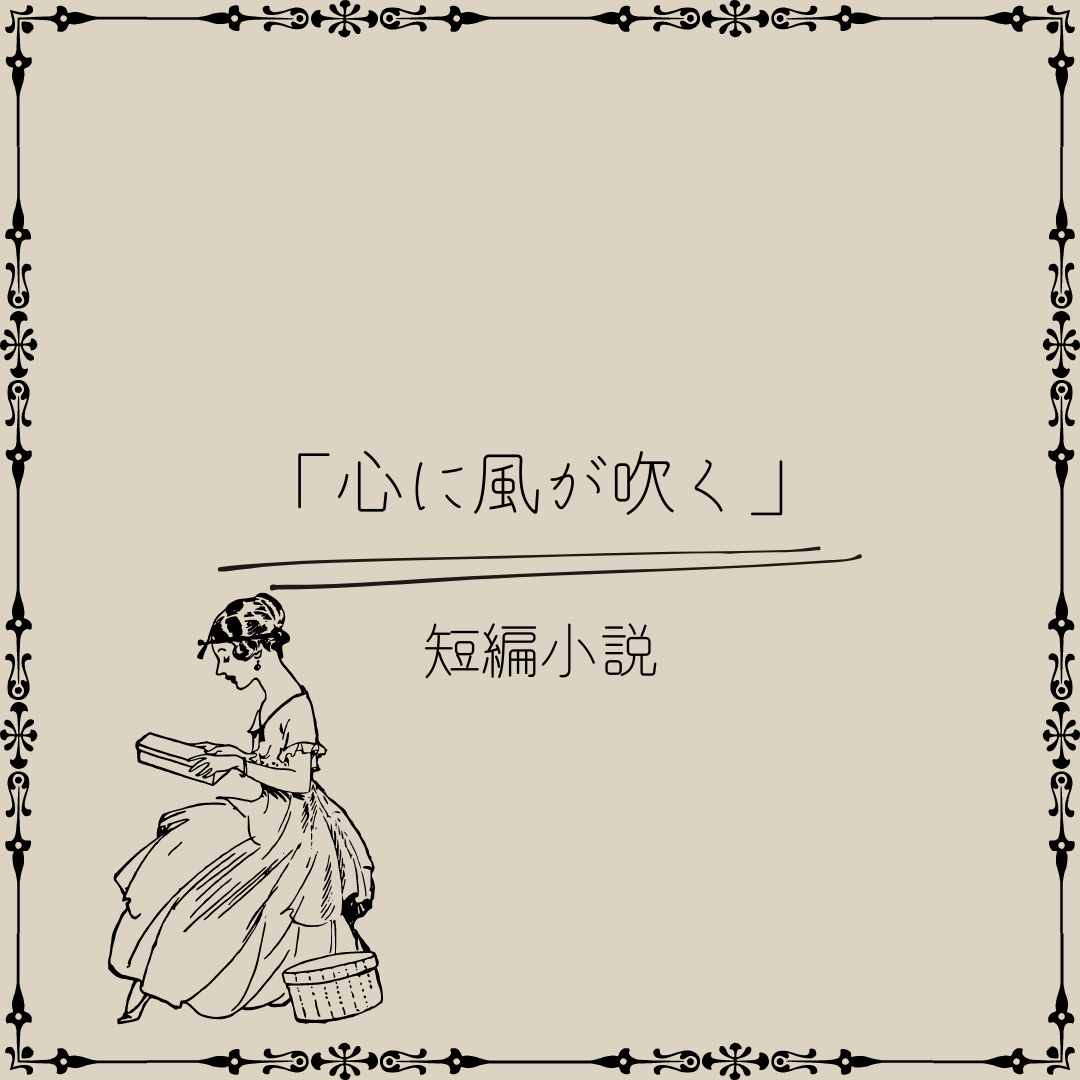


コメント