ダウンロード
本サイトに掲載している作品の無断複製、SNS・動画・その他サイトでの使用、自作発言等は禁止しています。
本文
「ウィリアム・ブラウン世紀の大発明!」
「彼の天才はノーベル賞受賞なるか!?」
「ノミネート後、授賞式には参加せず? 一体なぜ?」
「行方を眩ませた天才はどこへ行ったのか?」
……
「もう何年もこうしてメディアに取り上げられてばかりでは、滅入ります。何度もインタビューはお断りしたはずですが?」
「そんなこと言わないでくださいよ、ブラウンさん。巷じゃ、妻である貴女がウィリアムさんのことを隠してるんじゃないかって噂もあるんですよ」
「隠してる? それはどういうことです?」
「さぁ、それは貴女の方がよく知っているのでは?」
男は絶対に引かない姿勢を彼女に見せた。その様子に、これ以上の説得は無理だと諦めた彼女は一つの大きな溜め息をついて、彼を家に招き入れた。
「私も忙しいんです。時間は五分だけ。いいですね?」
「話がお聞きできるのなら、なんでもいいですよ」
そうして、五分のインタビューが始まった。成果としては、彼女は本当に何も知らないらしい。
「突然居なくなったんですよ。理由なんて知りません」
明らかに不機嫌になっていく彼女。聞く人が聞けば彼女が天才を殺したと思いかねない、ギリギリの発言を重ねていく。
「つまり、貴女はウィリアムさんが嫌いだったのですか?」
「嫌い……ではなかったわ。でも十年も音沙汰無しだと流石にね。普段から研究にばかり没頭していて、私の事なんてあまり考えていない人でしたから」
「そうですか……例えば、ひょっこり帰って来たりしたらどうします?」
「さぁ、どうするでしょうか。ひょっとしたら、家にあげないかもしれませんね」
そう不気味に笑う彼女。あぁこの人なら本当にやりそうだ、と思ったのは本人には言わなかった。
その十年後、また彼女を訪れた。一個人として。彼女への手土産に紅茶に合う菓子を持っていった。
「また来たんですか」
「……よく覚えてましたね。十年も前に一度来ただけなのに」
「覚えていますよ。あんなにしつこいのは貴方だけでしたから。それに、私は物覚えがいいんです」
「そうですか。ではあの時の無礼な行いも、貴女は覚えているわけだ」
「もちろんです。ですのでお帰りください」
「随分、酷いじゃあありませんか」
「どうせまた、夫が失踪した理由でも聞きに来たのでしょう?」
「ええ、個人的な興味がありまして」
「仕事ではなく?」
「ええ、ぜひ貴女の話が聞きたいのです」
彼女はまた、仕方なく、という感じで男を招いた。彼女の淹れたハーブティーは持ってきた菓子とよく合う。
「あの人は、ハーブティーなんて飲みませんでした」
「へぇ、それはどうして?」
「いつも仕事仕事って殆ど不眠不休で生きていましたから。コーヒーの方がよく飲んでいました。なんでも、ハーブティーを飲むと眠くなってしまうそうです。それはそうですよね、だって私はあの人がリラックスできるようにっていつもブレンドしていたんですから」
「……そうなんですね」
「私も何度かコーヒーを飲んでいますけれど、どうもあの苦味が好きになれないんですよ」
そう言った彼女は、少し憂鬱そうに窓の外を眺めていた。
また十年後。彼女の家を尋ねた。勿論、菓子を持って。その様子に彼女は
「お菓子を持ってくれば入れてくれると思っていません?」
と不服そうにしたが、前のように粘らずとも招かれた。出された紅茶を味わいながら飲んでいく。舌に乗ったほのかな苦味とそれを覆い隠すような果実の香りのする、不思議な味だった。
「私ね、最近はやっと諦めがつくようになったんです」
「と言いますと?」
「きっとあの人は、何か大切なものを見つけにいってしまったんだって」
「ほう?」
「もしかしたら、私よりも大切なものだったのかもしれませんね」
「どうして?」
「あの人が飲んでいたコーヒーを、最近飲んでみるんです。あの人からはいつもコーヒーの香りがしていた。前に、苦味が好きじゃないと言ったでしょう?でも、コーヒーには苦味以外にも酸味が強いものや渋味のあるもの、甘い香りがするものもあるんですよ」
彼女はこちらに、笑顔を向けた。
「コーヒーを飲もうとしていない時は、そんなこと知らなかった。あの人を知ろうとしていなかったから、私はあの人のことを何も知りません……そんな女、大切にされるはずがないでしょう?」
そうして、十年毎にお茶会を開いた。二十年後、三十年後と繰り返し開かれるお茶会。男は必ず菓子を持ってきた。彼女は必ず自慢のハーブティーと食後にコーヒーを淹れた。
「あの人は何を作ったんでしょうね」
「さぁ世紀の大発明と言われていましたからね」
「私、あの人の研究なんてこれっぽっちも気にしてなかったの。でも最近は考えるのよ。あの人が失踪した理由。その鍵は研究内容にあったんじゃないかって」
「彼の資料とか残ってないんですか」
「さぁ、どこにあるかもわからないの。研究者たちも、彼の失踪と共に論文もなくなってしまったと言うし……」
「どうして彼は隠したんでしょうね」
「わからない。だけど、彼は案外そばにいるような気がするのよ」
それから十年も経てば、彼女はすっかりとお婆さんになってしまった。もうほとんどベッドから起き上がれないのだという。部屋に入ると、薄暗い。しかし、一番大きな窓のそばに彼女は寝ていた。
「やぁ、お元気ですか」
「見ての通りですよ。今じゃ、もうすっかり動けなくなってしまった。老いるというのは恐ろしいですね」
「そうですか。今日はどうしましょう?なにか飲みますか?」
「いいえ、もういいわ。さっきまで介護士さんが私の世話をしてくれていたの。だからもういいわ」
「では、今日はどんなお話を?」
「そうねぇ……じゃあこんな話はどうかしら。タイムマシーンに乗っかって、時間を旅する男の話よ」
「……気づいていたんですね。すっかり目が見えなくなったと聞いたから、僕のこともわからないだろうと思っていたのに」
「初めから気がついていましたよ。気づかないわけがないでしょう?ずっと貴方を支えてきたのですから。誰よりも貴方のそばにいたのは私ですよ」
「そうか、それもそうだね」
「おかしいと思ったんですよ、貴方の姿がね。だって十年も前に流行ったファッションだった。時代遅れもいいところです」
「ファッションは……はは、関心がいかなかったなぁ」
「元々無頓着でしたものね。それに持ってきたカメラも古かった」
「そんなはずは……」
「ツメの甘いところは、昔からですねぇ。貴方は昔から何も変わっていませんが」
「そうかもしれないな」
「私、もうないと思っていたんですよ。貴方に見届けられるなんて。十年帰ってこなかった時は本当にそう思っていたの。でも、それから十年ごとに若い頃の貴方が来て、ひょっとしたら……なんて」
「ははは……」
「最初は貴方を恨んでいましたけど。でも、きっと貴方にも理由があったんだろうって思うようになったんです。だからその理由を聞くまでは、貴方とお茶会を開こうと思った。最期まで教えてくれませんでしたけどね」
「……君に言ってないことがあるんだ」
「そう」
ベッドに横になった彼女は、こちらを真っ直ぐ見つめた。握るように置いていた手に、彼女の手が重なる。老いてしまった手も視線も、昔と同じようにウィリアムを包み込む。窓から差し込む光は二人を照らし、白いシーツやシャツが眩しさを演出した。まるで、いつかの出会ったばかりの頃に戻ったような感覚だった。
長い沈黙の後、一つ息を飲んでから彼は続ける。
「僕は、癌なんだ。それも末期の」
彼女は目を見開く。そこには絶望はなく、穏やか。しかしその内には何かに安堵したような嬉しさも篭っていた。
「この旅を始める少し前に、医者に言われてね。もう寿命も長くないと言う。それを言われた時に、お先真っ暗。もうどうしたらいいかわからなかった」
「……」
「ずっと研究研究で君との時間を大切にしてこなかっただろう? その事を後になって悔やんだ。僕は君をずっとひとりぼっちにしてしまう。僕が死んだ後、きっと君は僕という枷に括り付けられたままだって」
彼女は静かに一つ一つを漏らさないように聞いていた。
「だから十年後の君に会いに行って、もう僕に縛られないで欲しいと言いに行こうとしたんだ。でも、君を見るとどうにも言えなくてね。ずるずるとここまで来てしまった」
「……」
「憎いだろう? 本当に君には申し訳ないことをしてしまった。最後まで。どうか、自由になって欲しかったんだよ」
「……そんな。そんな悲しいことを仰らないでくださいな」
昔のようには回らなくなった口で、今度は一言一言を丁寧に紡いでいく彼女。
「私は、貴方が優しいことを知っています。今日だって、私を……いえ、私と一緒に天国へ行ってくれるのでしょう?」
「……結果的にそうなってしまっただけなんだよ」
「でも、そのために貴方は来たんでしょう?」
「それは……」
「本当に愛しい人。嘘がつけない、正直な人。だから私は貴方を選んだの。そんな相手と一緒に最期を迎えるってこの上なく幸せな事だと、私は思うの」
いつの間にか、涙が零れていた。涙の粒は光を反射して、まるでビーズが散らばったようにシーツに落ちる。それはしみになって、深く深く糸の隙間に入っていった。
「死ぬことは怖い。でも貴方と一緒なら大丈夫だって思える。そうでしょう? 私の夫は、世紀の天才発明家だもの」
「僕も死ぬのは怖いよ。でも……ずっと僕だけを信じて待っていてくれた君のためなら、天国までエスコートしよう。その先も、今度は絶対にそばにいる。君に寂しい思いはさせないよ」
「あら、なんて紳士なのかしら。私って見る目があると思わない?」
「そうだね……でも、君の見初めた男もあまりいい男じゃないかもしれないな」
「あら、どうして?」
「だって君に、一度も『愛してる』って言えたことがないんだ」
そう言うと、彼女は若い頃となんら変わりのない、悪戯が成功したような笑顔を見せてきた。そうだ、僕はこの笑顔が好きで君を選んだんだ。
「その言葉も、貴方が言えるようになるまで、いつまでも待つわよ」
小高い丘の上の小さな家。庭には何種類ものハーブが植えられて、春には花が咲き美しい香りが漂ってくる。その家の、一番陽の当たる部屋で二人の男女が亡くなっていた。一人は老衰。一人は癌。息子と母ほど年の離れた二人は、同じ場所で今も眠っているという。
あとがき
ここまでご覧くださりありがとうございます。
「天才の発明品」は高校時代に部活の文芸誌「椎樹77」に掲載した作品です。
高校生の時から演劇を行っていたこともあり、台詞を多用した作品となっています。
懐かしいなと思いながらこちらのブログにも掲載いたします。
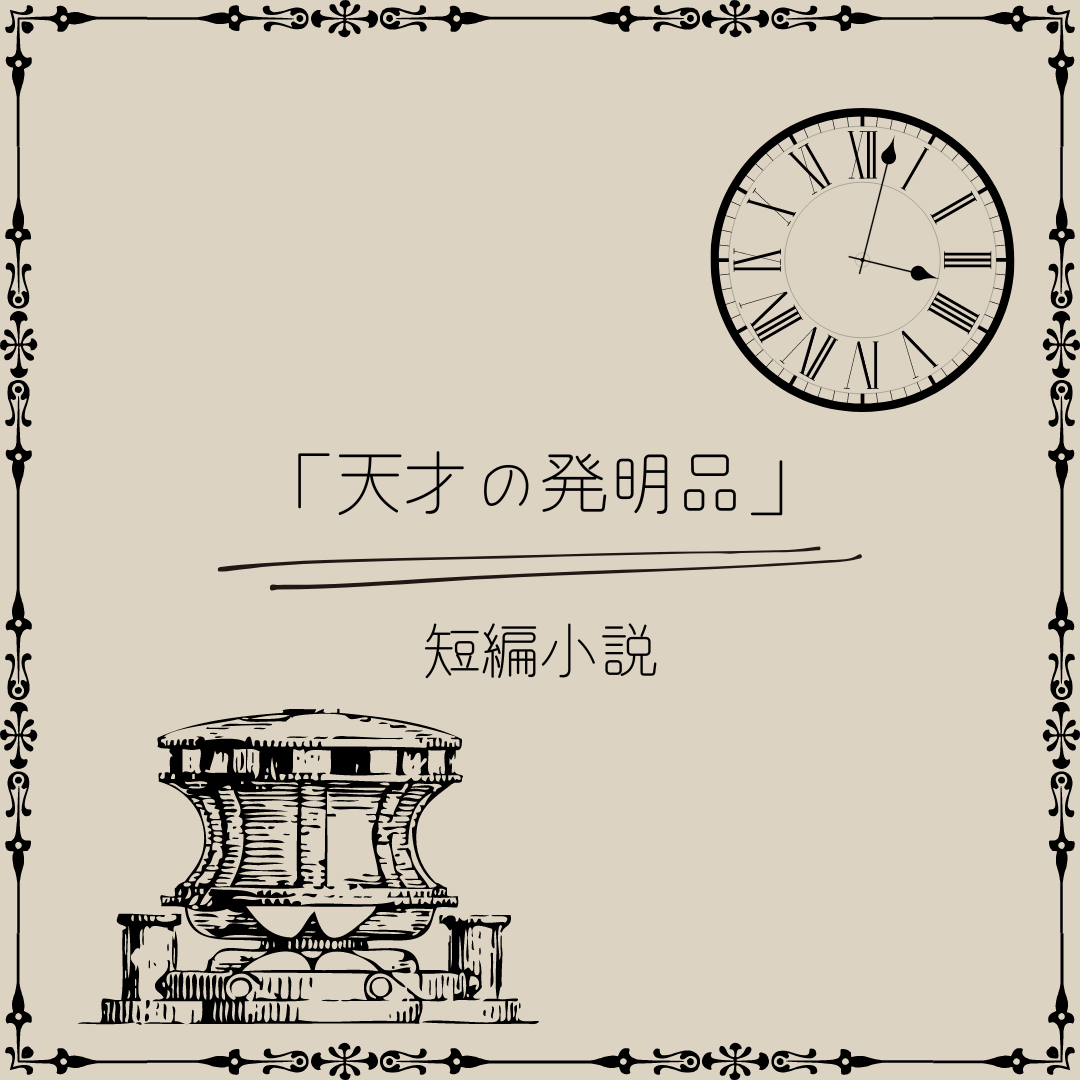
-1-1-120x68.png)
-120x68.png)
コメント