ダウンロード
本サイトに掲載している作品の無断複製、SNS・動画・その他サイトでの使用、自作発言等は禁止しています。
本文
不登校になりかけている従妹と桜祭りに出かけた。桜祭りと言っても、もう終盤で桜も葉桜になりかけている。就活に難航している私と、部屋に引きこもりがちな彼女と、見頃の桜を見られないのは仕方がない。
従妹は小学六年生で、もう随分切っていない長い前髪を手で避けながら桜を見ている。今日の服装は学校の体育着にジーパン。辛うじて学校に行こうという意志はあったようだ。意志はあっても、体が動かないこともある。それは私も一緒だった。
「アンタ、スーツも着ずにゴロゴロしてるなら桜見にでも行ってきなさいよ」
「うーん」
煮え切らない返事をしているとイライラしたように母は溜息をついた。当然だ、半年前から面接やらインターンやらを経験してきて、二十四戦、二十敗、四戦は結果待ちというところだ。けれどもあまり好印象はではないと思う。面接の受け答えも失敗してしまったな、と反省してしまうことばかりで、思い返したくもない。
「ほら、どうせやることないんでしょ。従妹でも連れて行ってきなさいよ」
そう言いながら母は叔母に連絡を取ったようで、スマホの画面を凝視しているのだった。
そうして引き合わされた私たちは当てもなく公園を散策するのだった。
「何か食べる? おごるよ?」
最近アルバイト代が入ったばかりの財布を見せる。従妹は少しばかり財布を見つめたが、すぐに首を振り俯いた。
風が吹く。桜が咲いていれば、桜吹雪でも起きそうなものだが、残念ながら葉桜だ。地面には花びらが積もっている。従妹は前髪を諦めたように同じようにアスファルトを見つめている。
「お姉ちゃんはお休みなの?」
「お、休み、と言えば、うん、まあ……」
「わたしはね、ずる休みなんだ」
ずる休み、と言いながら、彼女の顔色はあまり良くない。泣きそうな目、けれども泣くことを諦めてしまったような目をしていた。
「お姉ちゃんも、ずる休みと言えば、ずる休みなんだよ」
彼女は顔を上に向けた。まだまだ前髪が邪魔なようだ。風が吹くことで前髪から瞳をのぞかせた。少し焦げ茶色の目の奥に青い空が映る。
「本当はやらなきゃいけないことばっかりで、何にもせずにいたらお母さんに怒られちゃった」
「うん」
「だからね、こんな大人になっちゃだめだよ」
「……うん」
聞いているか、いないのかわからなかったがそのまま続けた。
「でも頑張り続けるのって苦しいよねぇ」
「うん、私、お姉ちゃんみたいになっちゃうんだろうなぁ」
お姉ちゃんみたいに、という言葉に引っ掛かってしまったけれど、今は言葉を遮ってはいけないだろう。言葉を上手く紡げない苦しさを、私もまだよく覚えている。
「どうして学校が怖いのかな」
直接聞くのは良くないことだと思いながら、言葉を選べなかった。彼女はアスファルトを見つめたまま足を止めている。
「宿題ができないの、算数がわからなくて」
アスファルトの上に落ちた花びらは多くの人に踏みつけられる。踏みつけられたところから、繊維が傷み、茶色く枯れ、腐っていく。その上にさらに新しい花びらが積もっていく。古い花弁は溶けて消える。
「算数わからない。わからないなら、答えを見なさいって言われるけど、分らなくて。周りの子はわかってるのに、私だけわからなくて、行きたくなくなっちゃうの」
一度感じたわからないものは、降り積もって、消えてはくれない。残り続けて、やがて石のように固くなって、鋭くなり胸を貫く。
「いじめがあったわけじゃない、私がただ、出来損ないなの。死にたいなぁ」
「そっか……」
「死にたいって、怒らないの?」
「怒らないよ、私も思うもの」
「ママは怒るよ」
「そりゃあねぇ、でも怒っても止められないよね」
彼女は小さくうなずいた。
算数程度で、と思うのは大人だからかもしれない。けれどそれを言ってしまえば、就職活動で立ち止まる私の悩みもきっと誰かには就活程度で、と思われてしまうのだ。就職活動が終わったら何だろうか、仕事か、転職か、昇進か。いつまでも終わらない問題が、いつまでも誰かに、その程度だと思われてしまう。この子が躓いたのが、たまたま今だっただけだ。
「桜ってね、仇花なんだって」
「あだばな?」
「咲いても実を結ばない、無駄な花って意味」
彼女の手を引いてゆっくりと歩きだす。素直に従ってくれる。白くまだらな地面を一つ一つ溶かすように。
「でもさ、無駄な花なのに、人間は育てるんだよ。倒れそうになったら支柱をたてて、添木で数を増やして、日本で育てる場所が無くなったら海外にあげたりしてさ」
「無駄なのに」
無駄なのに、美しいと思うから、それだけで。
「自分の人生が無駄だと思うから、死にたくなるんだよね」
何も残せないことが苦しくて死にたくなる。何もできないことが苦しくて死にたくなる。死にたくなっちゃいけないと考えて、余計に死にたくなる。その考え方が無駄だとわかっていても、考えてしまうから死にたくなる。
空を隠すように葉桜が枝葉を伸ばす。木陰が、花弁の積もる道の上に覆い被さる。目を閉じて、満開の桜を思い浮かべる。真っ白の景色を見上げた人たちが歩いていく。誰も彼も、皆、上を向いて歩いている。
花開いた桜は地面に向かって皆堕ちていく。
堕ちた花びらを見ているのは、下を向いた人しかいない。堕ちた花びらが消えていく、溶けていく様を目に留めているのは立ち止まった人しかいない。
「きっと、わたしたちにしかわからない、綺麗な景色があると、思いたいよね」
彼女はまた下を向いた。


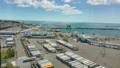

コメント